節約をしたり、副収入の方法を考えたりと、少しでも自由になるお金を増やしたいという方は多いのではないでしょうか。
であれば、やっておきたい3つの制度に、ふるさと納税、iDeCo、新NISAがあります。
今回はその1つ、『ふるさと納税』について解説したいと思います。
また別の記事にて残りの2つも紹介していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
『ふるさと納税』について話を持ち掛けると、よくこんな意見を聞きます。
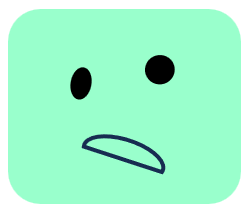
知っているけど利用したことない。
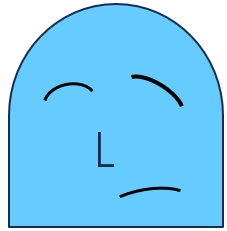
面倒なんでやらない
初めてのことというのは、始めるまで、なかなか行動に移せないというのはよく理解できます。
ですがこちらの制度で毎回やることは、次の2つです。
- ネットで商品を選んで注文する。
- 送られてきたA4用紙に必要事項を記入し返信する。(一部はオンラインでも処理可能)
この作業で商品とポイントの両方が手に入ります。
更に日用品を選べば、日々の節約ができるうえ、少し贅沢な商品によって生活が向上します。
利用できる方なら優先的に利用したい制度です。
制度の詳細を知りたい方は、下記のサイトをご参考下さい。
このあとに注意点など、もう少し詳細を説明しますので、ぜひこの制度を活用して下さい。
口座開設手順はMoney shipさんが詳しく解説されていますので ↓↓↓こちらをご覧ください。
ふるさと納税とは
おすすめの理由
ふるさと納税とは、
お住いの地域以外へ寄付(納税)することで、代わりにその地域の特産物や商品など(返礼品)が貰える制度
個人が追加で2000円を負担して払う必要がありますが、それ以上の金額の返礼品が受け取れるので、使わない手はないお得な制度です。
また複雑な手続きも必要ないため、1回やれば慣れてしまえる点もおススメの理由です。
- 返礼品の還元率が90%以上の商品もある。(還元率90%とは、寄付金1万円に対し9千円の商品が届くこと)
- 自己負担金は2000円のみで、寄付する数がいくつであろうと、寄付金額がいくら増えようと変わらない。
- 納税は先払いという形になり、支払った分は翌年の住民税から減額される。
制度のメリット、デメリット
メリット、デメリットは以下です。
- 地域の特産品が貰える
- クレジットカード、購入サイト、マイルなどのポイントがもらえる
- 日用品を選べば、生活費の節約ができる
- 好きな自治体に納税し、社会貢献できる
- 自己負担2000円がかかる
- 簡単であるが手続きが必要
- 減税、節税にはならない
- ワンストップ特例制度を適用できるのは5つの自治体まで。(それを超えると確定申告が必要)
確定申告をする手間が省ける制度です。A4用紙1枚程度の簡単な申請を提出する必要があります。
オンラインでできる自治体も増え、慣れれば5分とかからず記入できます。
ワンストップ特例制度を適用できるのは5つの自治体までですが、同じ自治体であればいくつ寄付しても、
「1つ」としかカウントされません。
ふるさと納税を利用する流れ
ふるさと納税のやり方を簡単に説明すると、
- ネットショッピングと同じように”楽天市場/さとふる/ふるなび”などで、「ふるさと納税」という項目の商品を選ぶ。
- ワンストップ特例制度にチェックを入れ、商品を購入する。
- 商品が届くので、ただ受け取る。
- 別でワンストップ特例制度の申請書類が届くので、必要事項を記入して返信する。(オンラインの場合もある)
- これを上限5つの自治体、もしくは上限金額になるまで繰り返す。
利用のコツや注意点
節約のワンポイント
ふるさと納税では地域の高級牛肉や海産物がもらえ、たまの贅沢を満喫できます。
ただし、「お金を増やす」という点から言えば、生活必需品を選ぶ方が、それなりの節約となります。
- お米
(現地発送の有名どころのお米が毎日食べられる) - トイレットペーパー
(普段では買えない良質な商品が手に入る) - ボックスティッシュ
(普段では買えない良質な商品が手に入る) - その他日用品
日々節約もできますが、加えて生活の質が向上します。
ただティッシュなどの日用品は大量に届く場合があるので、収納スペースに困ります。
収納スペースがないという方はご近所さんやお友達と話し合わせ、違う商品を購入し、物々交換(シェア)することで、収納スペースを必要とせず上手に活用することができます。
知っておいた方が良い注意点
いろいろお得な制度ですが、少しだけ注意点があります。
ここに注意
- 寄付金額には上限があり、年収のほか、扶養家族、医療費控除、住宅ローンによって変わる。
- 寄付金額上限額を超えると、その分は自己負担となり損するため、上限を超えないよう要注意。(楽天市場などのサイトで簡易計算が可能)
- 自分の住んでいる自治体から返礼品はもらえない(申込みはできるが商品は受け取れない)。
まとめ
この制度のデメリットといえば、はっきり言って2000円の自己負担くらいです。でもそれも、すぐに取り返せます。
手間といっても、普段、ネットで買い物をする方なら、おそらく慣れたものです。
このように気軽に利用できるうえ、日々の生活がちょぴり贅沢になる制度なのです。
利用しない手はないと思いますので、今日から全力で使い切りましょう。
――― おすすめの書籍 ―――
『このまま人生を終えるのか...』『変わるには何から始めれば?』とお悩みの方の一助となる「お金」の本を紹介します。これらの本は、単なるお金や投資の知識にとどまらず、人生を豊かにするヒントが詰まった本です。読むだけで人生の充実感がぐっと高まる、そんな魅力的な一冊をご紹介します。
>>日本人に限らず、多くの人はお金を貯めることに夢中になりがちです。働くことで時間を犠牲にし、賃金を得ていますが、そのお金を本当に使うべきタイミングはいつでしょうか?人生は生まれてから死ぬまで続きますが、お金の使える期間はそれよりずっと短いのです。それにもかかわらず、多くの人は将来の不安から使うタイミングを逃してしまいます。本書『DIE WITH ZERO』は、大切なのはお金そのものではなく、経験や挑戦を通じて得られる充実感であることを教えてくれます。また、お金の価値を最大限に引き出す最適なタイミングを示し、今しかできないことに投資する大切さを伝えています。普段は当たり前と思っている人生観を見直し、「充実して生きる」ことを考えさせてくれる一冊です。ぜひ後悔のない、納得のいく人生を発見してください。
>>本書は投資本として紹介されることが多いですが、実はお金の管理方法にも多くのページを割き、独自の視点で「時間」の大切さを説いています。つまり、投資のタイミングに頭を悩ませる時間を減らし、人生の貴重な時間を他の大切なことに使うべきだと説いています。
データに基づいた論理的な解説に加え、お金を貯めるための実践的な方法も網羅。シンプルでありながら説得力のある提案は、あなたの「お金」と「時間」の使い方を、より自由に、より豊かにする—。そんなヒントが詰まった良書です。
>>大学合格を祝う父から息子への心温まる手紙を元に、社会に出ていく若者に向けて社会で生き抜く知恵を伝える一冊です。著者は経済の視点から、お金や仕事、人間関係まで、 社会で生きていく上でのコツを、時にユーモアを交えながら語りかけます。たまに難しい金融用語が出てきますが、 まるで隣で優しい父親が話しかけてくるような語り口で、 すんなりと腑に落ちていくはずです。この本の真価は、経済という「物差し」を通して、 人生の本質を浮き彫りにしている点にあります。 20代の若者はもちろん、40代、50代の方々にも、 新鮮な気づきを与えてくれることでしょう。





