資産運用を始めるなら、「NISAで投資信託の積立購入」がポイントです。
投資を始める際は「知識を十分につけてから」という意見と「実践しながら学ぶ」という意見があります。
どちらも大切な考えですが、投資で最も重要なことは入金力 ✕ 時間です。
そこで、基本的な知識を理解した上で、少額からチャレンジができ、初心者でもすぐに始められる一例をご紹介します。
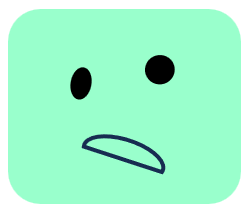
損したら責任取ってくれるの?
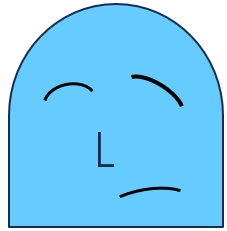
取りません。ただし
『買って学ぶ』、少額から
始められる投資を紹介します。
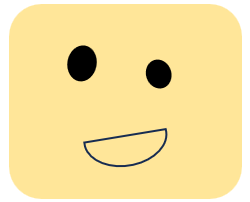
危なくないの?
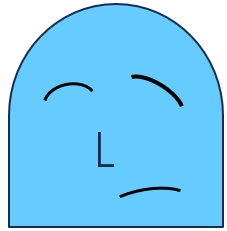
もちろんリスクはあります。
ですがリスクを抑えつつ、
利益が期待できる投資法です。
皆さんに決してやって欲しくないことは、投資を始めたはいいが、すぐに損をして投資の世界から退場してしまうことです。
投資なので運用する過程ではもちろんマイナスとなることはありますが、学びながら継続していくことで、トータルで利益を出す確率は高まります。
ここでの内容は、次のような方に適しています。
- まとまった資金があり運用を考えている
- 将来の資産形成のために投資を始めたい
- 投資や副業、何から始めようか迷っている
ここで紹介する3つの基本ツールは「NISA」、「投資信託」、「オルカン」です。
「オルカン」とは投資信託の商品の1つで、インデックス投資信託のeMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)の略です。
これらの特徴とメリット、そしてデメリットについて、順を追って詳しく説明していきます。
口座開設手順はMoney shipさんが詳しく解説されていますので ↓↓↓こちらをご覧ください。
3つの投資アイテムの特徴
まずは3つのアイテム「NISA」、「投資信託」、「オルカン」について、そのメリットを簡単に整理します。
- 利益が非課税
- 金融庁が厳選した安定的な商品
- 買い直しても手数料無料
- 低コスト
- 初めから分散投資された商品
- 最低100円から購入が可能
- 有名大企業にも投資できる
- 複利効果で資産が増える
- 積立設定で手間がかからない
- 年率リターンが約7%
- 米国を中心に全世界約50か国に分散投資
- 低コストの中でも最安値
デメリットについても、後半で説明していきます。
それでは解説していきます。
こういう人におすすめな理由
冒頭でも説明したように、次のような方に適しています。
- 貯金があり何か運用したい
- これから投資を始めたい
- 投資や副業、何から始めようか悩んでいる
貯金を運用したい
銀行で貯金している方は、インフレ(物価上昇)を意識したいです。
インフレとは、物の価格が上昇することですが、言い換えれば、年々お金の価値が下がっているということです。
自分が稼いだお金の価値を守るためにも、いち早くお金を物に交換することが大切です。
投資を始めたい
投資を始める際に必ず言われることは、投資を学んでリスクを理解するということです。
ただ投資といっても種類が多く、その内容とリスクを調べるには、そこそこ時間がかかります。
投資には運用時間が重要で、調べるばかりで始められない時間を過ごすことは、非常にもったいないです。
初めからオルカンという投資信託に絞れば、ネットでもYoutubeでも多く取り上げられているため、学ぶにも最小限の時間で済みます。
投資や副業で悩んでいる
先で説明したように、どの投資を始めるかでも時間がかかるのに、副業と比較していては何も始まりません。
また副業をしても、すぐに収益があげられるとは限りません。
時間を有効活用するためにも、まずは少額で運用を始め、その後に、より深く投資や副業を学習していきましょう。
NISAのメリット
利益が非課税
NISAで運用した場合、運用で得た利益は非課税となります。
たとえば100万円を投資して、1年後に110万円になったので売却した場合、利益は10万円ですが、そのうち手元に入るお金は8万円です。
利益10万円の場合、20%である2万円が税金として引かれるためです。(※実際、不労所得の利益20万円以内であれば税金はかかりません)
これがNISAでは非課税、つまり税金がかからず、10万円の利益がそのまま手元に入ります。
金融庁が厳選した安心な商品
NISA口座は、成長投資枠(上限240万円)とつみたて投資枠(上限120万円)という2つの枠があります。
この枠についての説明は省きますが、つみたて投資枠で買う商品は、金融庁が厳選した投資信託しか買えません。
金融庁が設定した条件をクリアした優良商品がラインナップされ、成績が悪かったり品質がよくない商品は排除されています。
買い直しても手数料無料
通常は投資商品を買う/売るという行為をした場合、証券会社に手数料を支払います。
ですが金融庁が厳選した商品には、売買手数料が無料という条件があります。
そのため失敗して買い直したいと思ったら、迷わず売って、買い直すことができます。
投資信託のメリット
投資信託には、アクティブ投資信託とインデックス投資信託の2つがあります。
ここではインデックス投資信託について、お話していきます。
低コスト
先ほど売買手数料は無料という説明をしましたが、信託報酬という運用手数料が取られます。
ですが、その手数料は0.1~0.5%と非常に安いです。(優良商品のみの数値。それ以上の手数料もあります)
たとえば信託報酬0.5%の場合、1万円買って1年間に支払う手数料は50円です。
0.1%であれば、更にお安くなります。
長期で運用する場合、手数料の影響も排除できない重要な要素です。
初めから分散投資された商品
インデックス投資信託は、まとまったグループ全体に投資する商品です。
たとえば日本では日経225といった日本のトップ225社だったり、米国ではS&P500といったトップ500社だったりです。
各企業への投資資金の割振りは商品によって異なりますが、既に分散投資がされている商品となります。
なので損得の振り幅が小さく、リスクが抑えられた商品になっています。
最低100円から購入が可能
人気な投資信託の多くは100円から購入できます。毎月でも良いですが、毎日100円ずつ購入することも可能です。
有名大企業にも投資できる
最小購入単位は100円ですが、それでトヨタやユニクロに投資できます。
米国ではGAFAMといってGoogle、Amazon、Facebook、Apple、Microsoftなどの超有名企業に、100円で投資できます。
ただし、これらの有名企業に投資できるといっても、その企業の株式を直接買うのではありません。
それらの銘柄を含む投資信託を買うことになります。
株式の平均株価は、これら有名企業が引っ張っています。その株式を少額から買えるのです。
複利効果で資産が増える
株式に投資している投資信託では、毎年数回程度、分配金が出ます。
投資している企業からのお小遣い(利息)のようなものです。
また分配金を受け取れる商品もありますが、自動で再投資される商品もあります。
自動で再投資される商品については、利息が利息を呼ぶ複利効果で、資産が勢いよく増えることになります。
積立設定で手間がかからない
証券会社によって差はありますが、投資信託の購入を毎日や毎月、決まった額を自動積立設定できる機能があります。
設定も簡単で、完了すればその後は何もする必要がなくなり、「ほったらかし」で運用が可能です。
オルカンのメリット
年率リターンが約7%
オルカンの過去30年間の年率リターンは6~10%と言われます。ただ市場が好調/不調だったり、どの期間で切り取って計算するかで大きく異なるので、一概にこの数値というのは出しにくのが現実です。
ただ別のベンチマークであるS&P500の過去50年の年率リターンは10.5%なので、オルカンの構成品目から考慮しても約7%は妥当な数値と考えます。
年率リターンを7%として100万円を投資したら、1年後には107万円となり7万円の利益が得られます。
ミドルリスク・ミドルリターンの商品です。
米国を中心に全世界約50カ国に分散投資
投資において、リスク対策として重要なのは分散投資です。
現在の世界経済の中心は米国であるため、オルカンの投資先の6割は米国、残りがそれ以外の国となっています。
ただ今後、米国が衰退していく可能性が0(ゼロ)とは言い切れません。
オルカンでは世界情勢によって投資先が自動で見直されますので、何もすることなく、常にバランスの取れた、最適な分散投資が行われます。
低コストの中でも最安値
インデックス投資信託の信託報酬が年率0.1~3%と言われるなかで、オルカンは0.05775%と業界最安値の一角です。
実際には他にもコストがかかるため、最終的な実質コストは0.113%ですが、トップクラスの安いコストとなっています。
手数料が安いのは、その商品の自信の表れでもあります。
デメリット
今回紹介する投資法は、通常の株式投資に比べ、デメリットがかなり減っています。
そのなかでデメリットを挙げると次のようなものになります。
投資とは、リスクを負った人に利益をもたらしますが、ときにはマイナスとなります。
この商品に限らず、株価は毎年のように平均で約15%の下落が、一時的に発生しています。
現在は米国中心の構成銘柄であるため、米国の景気が悪化すると大きなダメージを受けます。
オルカンは外貨資産が大半を占めるため、円高が進むと利益が減ります。
オルカンに限らず、株式投資において一般的に挙げられるデメリットばかりです。
これらは一時的に発生する要素が多く、オルカンのメリットにより次第にバランスされ、長期運用を行うことでリスクが低減します。
まとめ
「ほとんどの市場は、ほとんどの期間、上昇している」
これは著書「JUST KEEP BUYING」からの引用です。
誰でも投資となると下落を怖れますが、それは一瞬だったり、短期間です。
重要なのは右肩上がりの流れにできるだけ早く、そして長く乗ることです。
人によってリスク許容度は異なるため、いきなり100万円を投資する人がいれば、毎月100円を投資する人もいます。
まずは「マイナスとなっても続けられる金額」=「自分の許容できる金額」で始めてみましょう。
みなさんが豊かな人生を送るために大切なことは、投資を学ぶこと、そして決してそこから退場しないことです。
まずはリスクを抑えた少額投資からチャレンジしてみてください。
【その他のおすすめ関連記事】
【新NISA】SBI証券と楽天証券の口座開設方法~投資信託のオルカンを購入するまでを簡単解説
新NISA時代のインデックス投資入門|世界の投資家が選ぶ資産形成の最適解
――― おすすめの書籍 ―――
『このまま人生を終えるのか...』『変わるには何から始めれば?』とお悩みの方の一助となる「お金」の本を紹介します。これらの本は、単なるお金や投資の知識にとどまらず、人生を豊かにするヒントが詰まった本です。読むだけで人生の充実感がぐっと高まる、そんな魅力的な一冊をご紹介します。
>>日本人に限らず、多くの人はお金を貯めることに夢中になりがちです。働くことで時間を犠牲にし、賃金を得ていますが、そのお金を本当に使うべきタイミングはいつでしょうか?人生は生まれてから死ぬまで続きますが、お金の使える期間はそれよりずっと短いのです。それにもかかわらず、多くの人は将来の不安から使うタイミングを逃してしまいます。本書『DIE WITH ZERO』は、大切なのはお金そのものではなく、経験や挑戦を通じて得られる充実感であることを教えてくれます。また、お金の価値を最大限に引き出す最適なタイミングを示し、今しかできないことに投資する大切さを伝えています。普段は当たり前と思っている人生観を見直し、「充実して生きる」ことを考えさせてくれる一冊です。ぜひ後悔のない、納得のいく人生を発見してください。
>>本書は投資本として紹介されることが多いですが、実はお金の管理方法にも多くのページを割き、独自の視点で「時間」の大切さを説いています。つまり、投資のタイミングに頭を悩ませる時間を減らし、人生の貴重な時間を他の大切なことに使うべきだと説いています。
データに基づいた論理的な解説に加え、お金を貯めるための実践的な方法も網羅。シンプルでありながら説得力のある提案は、あなたの「お金」と「時間」の使い方を、より自由に、より豊かにする—。そんなヒントが詰まった良書です。
>>大学合格を祝う父から息子への心温まる手紙を元に、社会に出ていく若者に向けて社会で生き抜く知恵を伝える一冊です。著者は経済の視点から、お金や仕事、人間関係まで、 社会で生きていく上でのコツを、時にユーモアを交えながら語りかけます。たまに難しい金融用語が出てきますが、 まるで隣で優しい父親が話しかけてくるような語り口で、 すんなりと腑に落ちていくはずです。この本の真価は、経済という「物差し」を通して、 人生の本質を浮き彫りにしている点にあります。 20代の若者はもちろん、40代、50代の方々にも、 新鮮な気づきを与えてくれることでしょう。



