生活をしていると、たびたび決断を迫られる場面に遭遇します。たとえば
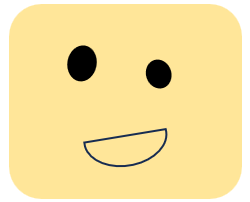
今買うべきか、待つべきか、
どっちにしよう?
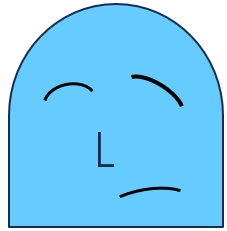
やってから考えるか
考えてから始めるか
どっちでいこう?
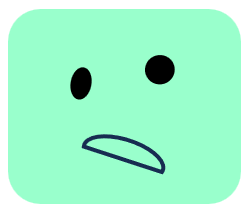
いっそうのこと言っちゃおうか
それともまだ黙っておこうか
どうしよう?
ただ人間は、計算上では損得がはっきりしているのに、心理的な影響からおかしな選択をするそうです。
とくに投資をやっていると、狂ったように「おかしな選択」ばかりしてしまいます。
冷静に考えれば得をする方を選べるのに、条件や状況によって損をする方を選んでしまう。
お金にまつわる不合理な人間の行動や心理について、設問形式で読み解いて行きます。
目次 閉じる
口座開設手順はMoney shipさんが詳しく解説されていますので ↓↓↓こちらをご覧ください。
あなたなら どれを選択
人の行動パターンを分析した理論があります。順に見ていきましょう。
プロスペクト理論
人はとにかく損をすることが嫌いなため、それを避けようとします。
ですが、その影響で結果的に損をする方を選んでしまうようです。
言葉を噛まないようにゆっくり喋ってたら、うっかり舌噛んじゃったみたいなことですけど、かなり鈍臭いですよね。
でも、やっちゃうんです。
この理論では2つのタイプがあります。設問でみていきましょう。
あなたはどちらを選びますか?
A.確実に10万円がもらえる。
B.コインを投げて表が出たら30万円もらえる。裏ならもらえない。
この設問では、ほとんどの人が上のAを選びます。
こういう設問は、その事象を10回繰り返すと損得が分かりやすくなります。
Aを10回繰り返すと、100万円が自分のものとなります。
一方Bでは、コインの表か裏が出る確率は2分の1なので、10回やると5回は表が出て、150万円が手に入ります。
Bの方がお得なのに『損をするのが嫌』という心理が強く働き、少ない方のAを選択するのです。
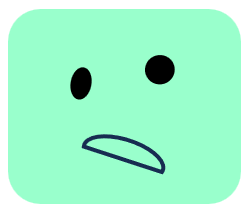
少なくても得するのに変わりないから
Aでいいじゃん。
その通りです。もともと無かったお金なんで、貰えるだけマシですね。
では次の状況ではどうでしょう。
C.確実に10万円が税金として取られる。
D.コインを投げて表が出たら30万円取られる。裏なら税金を払わなくて良い。
先ほどのように10回繰り返して考えると、Cの損失は-100万円、一方のDは-150万円です。
ですが確実に損するCを避け、ほとんどの人が支払いから逃れる可能性のある下のDを選択します。
結果的には損失が大きくなってしまいます。
初めの設問『リスク回避型』のように、得をするときは確実な利益を得る選択をします。
なのに2つ目の設問『損失回避型』のように、損をするときは計算上の損得ではなくギャンブルをしてしまうのです。
どちらでも大きく損をしてしまうなんて、どんだけ不幸なんでしょう。もったいない〜〜〜
確率的思考
次ではどれを選びますか。
A.100%の確率で10万円が手に入る。
B.70%の確率で30万円が手に入る。
C.20%の確率で100万円が手にはいる。
プロスペクト理論の説明で もうお分かりだと思いますが、これも10回繰り返してみましょう。
Aは10回全てもらえるので、
10回 ✕ 10万円 = 100万円
Bは10回のうち7回もらえるので、
7回 ✕ 30万円 = 210万円
Cは10回のうち2回もらえるので、
2回 ✕ 100万円 = 200万円
確率的思考とは、勝てる確率が最も高い戦略を追い求める思考法です。上の結果、一番もらえる金額が多いBを選択した方が良いことになります。
何も知らないとAを選んでしまう人もいると思いますが、確率的にはAの効率が最も悪く、Cのギャンブル的思考にも大差をつけられてしまいます。
チャンスは1回だけと考えた人と、チャンスは何度も巡って来ると考えた人とでも、答えは違ってきそうです。
サンクスコスト効果
あなたは映画館で1800円を払って上映2時間の映画を見始めました。
ところが開始30分でこの映画がつまらないことに気付きます。
このときどうしますか。
A.時間がもったいないので映画館から出る。
B.1800円がもったいないので最後まで見続ける。
このどうやっても取り戻すことができない『映画代1800円』と『最初の30分』の損失を、サンクスコストと言います。
この設問では、ほとんどの人が下のBを選びます。
上のAを選んで他に楽しいことをするべきですが、既に払ったお金を無駄にしたくないという気持ちが働き、最後まで映画を見続けてしまいます。
とは言え『ここから面白くなるかも』って期待するので、なかなか途中で止めるってのも難しいですよね。
『どうやって1800円を取り返そう』と考えてるうちに、映画が終わってしまいそうですし。
現状維持バイアス
お昼に少し時間が空いたので、一人で昼食を食べに行きます。どちらを選びますか。
A.いつも行っているお気に入りのとんこつラーメン1杯800円
B.高層ビル最上階からの景色を眺めながら、超格安 丸ごと蟹ラーメン1杯1000円
新しいことにチャレンジしようとする場合、得すると分かっていながら損する可能性に意識が集中し、最終的に現状のままでいることを選択してしまうという心理です。
「混んでるのでは?」や「この服装で大丈夫?」のように不安になり、結局のところ「行ってはみたいけど面倒くさい」ってよくなる光景ですね。
また魅力的な選択肢が増えれば増えるほど人は「何もしない」という行動をとることを『決定麻痺』と言い、これも理論の1つです。
なので上のAを選ぶ人が多いようです。
まとめ
人の心理が働くと、計算上は損得がはっきりしているのに合理的でない方を選択してしまいます。
この人間行動学を今からでもイメージをしておけば、何か選択する場合に1度立ち止まって考え、もしかすると良い選択ができるかもしれません。
1度なら大したことないかもしれませんが、正しい決断を積み重ねることで、大きな成果を生むこともあります。
役立つときが来るまで、頭の片隅にでも意識してみて下さい。
――― おすすめの書籍 ―――
『このまま人生を終えるのか...』『変わるには何から始めれば?』とお悩みの方の一助となる「お金」の本を紹介します。これらの本は、単なるお金や投資の知識にとどまらず、人生を豊かにするヒントが詰まった本です。読むだけで人生の充実感がぐっと高まる、そんな魅力的な一冊をご紹介します。
>>日本人に限らず、多くの人はお金を貯めることに夢中になりがちです。働くことで時間を犠牲にし、賃金を得ていますが、そのお金を本当に使うべきタイミングはいつでしょうか?人生は生まれてから死ぬまで続きますが、お金の使える期間はそれよりずっと短いのです。それにもかかわらず、多くの人は将来の不安から使うタイミングを逃してしまいます。本書『DIE WITH ZERO』は、大切なのはお金そのものではなく、経験や挑戦を通じて得られる充実感であることを教えてくれます。また、お金の価値を最大限に引き出す最適なタイミングを示し、今しかできないことに投資する大切さを伝えています。普段は当たり前と思っている人生観を見直し、「充実して生きる」ことを考えさせてくれる一冊です。ぜひ後悔のない、納得のいく人生を発見してください。
>>本書は投資本として紹介されることが多いですが、実はお金の管理方法にも多くのページを割き、独自の視点で「時間」の大切さを説いています。つまり、投資のタイミングに頭を悩ませる時間を減らし、人生の貴重な時間を他の大切なことに使うべきだと説いています。
データに基づいた論理的な解説に加え、お金を貯めるための実践的な方法も網羅。シンプルでありながら説得力のある提案は、あなたの「お金」と「時間」の使い方を、より自由に、より豊かにする—。そんなヒントが詰まった良書です。
>>大学合格を祝う父から息子への心温まる手紙を元に、社会に出ていく若者に向けて社会で生き抜く知恵を伝える一冊です。著者は経済の視点から、お金や仕事、人間関係まで、 社会で生きていく上でのコツを、時にユーモアを交えながら語りかけます。たまに難しい金融用語が出てきますが、 まるで隣で優しい父親が話しかけてくるような語り口で、 すんなりと腑に落ちていくはずです。この本の真価は、経済という「物差し」を通して、 人生の本質を浮き彫りにしている点にあります。 20代の若者はもちろん、40代、50代の方々にも、 新鮮な気づきを与えてくれることでしょう。



