近年、投資への関心が急速に高まり、これまで投資に縁遠かった人々の間でも「株式」という言葉が日常的に聞かれるようになりました。
日常的なニュースでも頻繁に取り上げられる株式市場。多くの人が「なんとなく知っている」「なんとなく分かっている」という程度の理解で、実際に株式投資や投資信託を始めている場合も少なくないのではないでしょうか。
しかし、この「なんとなく」という理解のレベルは、実際の投資活動を行う上で十分なのでしょうか。私たちが「知っているつもり」の中には、意外な盲点や誤解が潜んでいるかもしれません。
そこで株式について、基本的な要点を整理してみましょう。
- 株とは「株式(かぶしき)」の略である。
- 株を購入すると、その会社のオーナー(株主(かぶぬし))になれる。
- 証券会社で購入できる。ただし購入できるのは「上場株式」のみ。
- 1株単価を株価といい、証券取引所が開いているあいだ常に価格が変動する。
- 株を売買すれば利益を得られる。(損することもある)
- 株主は配当金や株主優待を受取ることができる。
次のようなサイトもありるので、参考にしてみてください。
この記事では投資初心者の方に、これらの基礎知識をより詳しく、分かりやすく解説していきます。「なんとなく」から「確かな理解」へと、一緒にステップアップしていきましょう。
目次 閉じる
口座開設手順はMoney shipさんが詳しく解説されていますので ↓↓↓こちらをご覧ください。
株とは?
株(かぶ)とは「株式(かぶしき)」の略です。
会社が事業を始めるのにお金が必要となりますが、そのお金を出資してくれた投資家(出資者)に、出資の証明書として発行したものが「株式」です。
少し簡単に言うと、会社が事業を始めるためにチケット(株式)を売って、お金を集めることです。
この株式を発行した会社を株式会社と言い、お金を出資した投資家は株主(かぶぬし)となります。
株式には、1人の出資者で事業を始めるより、多くの出資者から資金を調達することでリスクを減らせるという利点もあります。
以降の文章に出てくる「会社」は、「株式会社」を指します。
株式は本来、紙で発行される券面でしたが、2009年1月の株券の電子化により紙の証券はなくなり、現在は電子名簿上に出資や権利の証拠が記録されています。
株式を保有するとは
株式を保有することで、その会社の株主になります。つまり株主とは、その会社のオーナー(所有者)です。
ただし株主は経営者ではないため、直接事業を行いません。
株主の主な権利には次のようなものがあり、株式の保有数が多ければ多いほど、権限も大きくなります。
- 取締役の選任・解任を含め、会社に関する重要事項を決定する権利
- 会社が得た利益の分配を受け取る権利
- 会社が解散/倒産したときに負債を清算後の財産を受け取る権利
ちなみに経営者とは、株主の代理人として会社の経営を行う人で、会社の利益を最大化するため経営方針や戦略などの意思決定を行う人です。要するにここで言う経営者とは社長です。
社長は大きく分けて、オーナー社長とサラリーマン社長の2つタイプに分けられます。
オーナー社長とは自身で資金を出し会社を創業し、経営の最終的な決定権を持つ経営者を言います。
一方サラリーマン社長は『雇われ社長』で、オーナーもしくは株主の代理人として会社の経営を行う人です。
株式会社の場合、株式の保有数によって立場が決まり、発行済み株式の51%以上を保有していれば「普通決議」を単独で成立させることができるためオーナー社長と言えます。
実際の会社の事業を行うのは経営陣ですが、株主はその経営方針に意見できるという強い立場なのです。
会社は株主のものなのです。
株主の責任とは
仮に会社に何かあっても、出資額以上の責任を負うことはありません。
不正が発覚して社長が頭を下げている映像をたまに見ますが、基本、株主への責任追及はありません。
会社が多額の負債を抱えて倒産したとしても、株主は出資額全額を損失することはあっても、その範囲を超えて会社債務の返済義務を負うようなことはありません。
言うなればスポーツ観戦の年間チケットを買って、好きなチームを応援したり、ヤジを飛ばしているようなものです。
違うのはチームが勝ち続ければ、お金を貰えるし、そのチケットを高く売ることさえできるってことです。
そう考えると、かなりお得です。
ただその逆で負ければ損失も出るので、応援するにもそれなりの覚悟と責任が必要となります。
株式はどこで手にはいる?
日本では4つの証券取引所(東京、名古屋、札幌、福岡)で株式の取引が行われます。
ただし個人が直接、証券取引所で購入することはできず、購入する場合は証券会社を通して購入します。
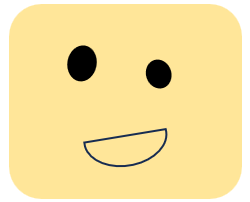
なんで大阪が無いの?
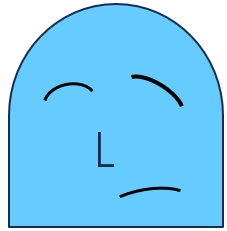
かつては大阪にもあったんです
興味ある方は、この項目最後の
説明をご覧ください。
証券会社とはSBI証券や楽天証券などです。ネット上で気軽に取引が可能です。
また購入できるのは上場(じょうじょう)している会社の株式で、一般に公開されていない未公開株式は購入できません。
「上場」とは、一定の基準をクリアして証券取引所で株式を自由に売買できることを言います。
たとえば普段お店で買う商品は、卸売市場に直接行っても個人で商品は買えず、仲卸業者が仕入れたものを店頭で買いますが、株の購入も同じイメージです。
ただし株の場合、証券会社を通すと言っても、注文してから売買するまで、非常に短時間で行うことができます。早ければ数秒で売買が成立します。
株式の取引ができる時間帯は、証券取引所が開いている土日祝日や年末年始を除く平日の前場(ぜんば)9時~11時30分、後場(ごば)12時30分~15時となります。
かつて大阪にも大阪証券取引所がありました。
1879年に開かれ、2013年7月12日に株式取引が終了まで134年間開かれていましたが、東京証券取引所に経営統合されたようです。
株価とは
株価(かぶか)とは、株式1株の時価を指します。証券取引所で売り注文と買い注文の売買が成立したときの価格です。
証券取引所が開いているときに売買が行われ、その間、株価は変動します。
株価が決まるのは、オークション取引といって株式の売り注文と買い注文である需要と供給のバランスが取れた水準になったときです。
買い注文が多ければ株価は上がりますし、逆に売り注文が多ければ株価は下がります。
株主である投資家が、会社業績、金利、為替(かわせ)、国内外市場動向などさまざまな要因を考慮して売買を判断するため、価格は常に変動します。
ちなみに日本で購入する場合は最低単元株式数(たんげんかぶしきすう)である100株単位でしか株を購入できません。
一方、米国の株も購入可能で、米国株なら1株単位で購入できます。
株式はなぜ得する?損する?
株式は、安いときに買って高いときに売れば、その差額が利益となります。
その逆で安くなって売ると、その差額分の損失が出ます。非常に単純です。
また株にもよりますが、配当金(はいとうきん)や株主優待(かぶぬしゆうたい)がもらえます。
配当金とは会社で出た利益から、株式の保有数に応じてお金が支払われる仕組みで、配当金の回数は年2回が一般的です。
会社によっては無配(むはい)と言って配当を行わない会社も存在します。
一方、株主優待とは、自社商品やサービスを無料で提供したり、割引クーポン券を配布したりして、株主を優遇する仕組みです。
現金がもらえるわけではありませんが、お金以外でお得感を味わえます。
配当金や株主優待が高額となっている株を購入する場合には注意が必要です。
なぜなら人気を取りたいがため(株価を下げないため)に高額としている会社も存在するからです。
配当金などは会社の利益から還元されます。
もし赤字ならどんどん資産が減り、負債が大きくなっている危ない会社という可能性もあります。
まとめ
株について要点を絞って解説しましたが、どうだったでしょうか。おおよそ思った通りの内容だったでしょうか。
株とは資金を集める手段であり、株を買うことで気軽にその会社のオーナーになれます。
ちょっとしたスポーツ観戦の年間チケットのようなものですが、観戦もできる上に損得が発生します。
言い換えると損得が無ければ、よくあるチケットと同じであり、この損得が株式の醍醐味と言えるかもしれません。
注意してもらいたいのは、株は博打(ばくち)ではありません。 株は投資です。
これから育っていく優良企業を応援しながら、私たちも一緒に豊かになれる魔法のような商品です。
投資であることを意識して、宝探しをするように、良い企業を発掘してはいかがでしょか。
――― おすすめの書籍 ―――
『このまま人生を終えるのか...』『変わるには何から始めれば?』とお悩みの方の一助となる「お金」の本を紹介します。これらの本は、単なるお金や投資の知識にとどまらず、人生を豊かにするヒントが詰まった本です。読むだけで人生の充実感がぐっと高まる、そんな魅力的な一冊をご紹介します。
>>日本人に限らず、多くの人はお金を貯めることに夢中になりがちです。働くことで時間を犠牲にし、賃金を得ていますが、そのお金を本当に使うべきタイミングはいつでしょうか?人生は生まれてから死ぬまで続きますが、お金の使える期間はそれよりずっと短いのです。それにもかかわらず、多くの人は将来の不安から使うタイミングを逃してしまいます。本書『DIE WITH ZERO』は、大切なのはお金そのものではなく、経験や挑戦を通じて得られる充実感であることを教えてくれます。また、お金の価値を最大限に引き出す最適なタイミングを示し、今しかできないことに投資する大切さを伝えています。普段は当たり前と思っている人生観を見直し、「充実して生きる」ことを考えさせてくれる一冊です。ぜひ後悔のない、納得のいく人生を発見してください。
>>本書は投資本として紹介されることが多いですが、実はお金の管理方法にも多くのページを割き、独自の視点で「時間」の大切さを説いています。つまり、投資のタイミングに頭を悩ませる時間を減らし、人生の貴重な時間を他の大切なことに使うべきだと説いています。
データに基づいた論理的な解説に加え、お金を貯めるための実践的な方法も網羅。シンプルでありながら説得力のある提案は、あなたの「お金」と「時間」の使い方を、より自由に、より豊かにする—。そんなヒントが詰まった良書です。
>>大学合格を祝う父から息子への心温まる手紙を元に、社会に出ていく若者に向けて社会で生き抜く知恵を伝える一冊です。著者は経済の視点から、お金や仕事、人間関係まで、 社会で生きていく上でのコツを、時にユーモアを交えながら語りかけます。たまに難しい金融用語が出てきますが、 まるで隣で優しい父親が話しかけてくるような語り口で、 すんなりと腑に落ちていくはずです。この本の真価は、経済という「物差し」を通して、 人生の本質を浮き彫りにしている点にあります。 20代の若者はもちろん、40代、50代の方々にも、 新鮮な気づきを与えてくれることでしょう。



